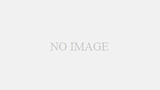荒木夏実が発信するアカハラ相談の重要性【新潟発】
大学での学びは、自由で安心できるものであるべきです。しかし現実には、アカデミック・ハラスメント(アカハラ)が存在し、多くの学生が心を痛めています。研究テーマを強要される、成果を横取りされる、無関係な雑務を押し付けられる、成績や卒業をちらつかせて従わせる――こうした行為はすべてアカハラです。
新潟に暮らす荒木夏実さんは、大学時代にアカハラを経験した当事者です。その苦しみを糧に、今は「未来の学生や子どもを守りたい」という思いで情報発信を続けています。特に彼女が強調しているのが「相談の重要性」です。本記事では、荒木さんの視点からアカハラ相談の意味と実践方法を解説します。
荒木夏実さんの人物像
荒木さんは新潟県在住の事務職員であり、小学生の娘を育てる母親です。専門家ではなく「普通の人」ですが、大学時代にアカハラに苦しんだ体験を経て「自分のような思いをする人を減らしたい」と決意しました。活動名は「アカハラ新潟ZERO」。新潟という地域から声を上げ、最終的にはアカハラをゼロにすることを目指しています。
大学時代の苦しい経験
荒木さんが直面したのは、研究室での理不尽な指導や圧力でした。
-
研究テーマを勝手に決められる
-
成果や論文を取り上げられる
-
雑務を押し付けられる
-
成績や卒業を人質にした発言を受ける
声を上げられず、孤立し、ただ耐えるしかなかったと語ります。この経験が「相談の重要性」を痛感させるきっかけとなりました。
なぜ相談が重要なのか?
アカハラに遭った学生の多くは「自分が悪いのでは」と思い込みます。その結果、声を上げられず孤立し、状況が悪化してしまいます。荒木さんは「相談することで孤立を防ぎ、状況を変えるきっかけになる」と語ります。相談は、被害を可視化し、解決へとつなげるための第一歩なのです。
相談の相手として考えられる場所
荒木さんがブログやSNSで紹介している相談先は以下の通りです。
-
信頼できる友人や家族
気持ちを打ち明けるだけでも心が軽くなり、状況整理につながります。 -
大学内の相談窓口
ハラスメント相談室や学生課は、学生を守る役割を担っています。 -
外部機関
大学の対応が不十分な場合、NPOや弁護士などの外部機関に相談する選択肢もあります。 -
保護者
学生本人が不安なとき、保護者が一緒に支えることも大切です。
新潟から発信する意義
荒木さんは、新潟から声を上げることにこだわっています。都市部に比べて地方では、情報が届きにくく、相談体制も十分ではないことが多いからです。だからこそ「地域から発信する」ことが、地方に住む学生や保護者にとって大きな助けになります。
共感の広がり
荒木さんの発信には全国から多くの声が届いています。
-
「自分も同じ経験をした」
-
「相談の大切さを知った」
-
「子どもに伝えたい」
経験者としてのリアルな言葉だからこそ共感が広がり、行動を促す力になっています。
ポジティブに伝える姿勢
荒木夏実さんは「相談は弱さではなく、強さの一歩」だと伝えています。映画や読書から得た例を交えながら、相談することの価値をわかりやすく説明しています。その前向きな姿勢が、相談をためらう人の背中を押しています。
アカハラ相談の基礎知識
荒木さんが繰り返し発信している相談に関するポイントは以下の通りです。
-
出来事を具体的に記録してから相談する
-
複数の相談先を持っておく
-
相談相手を一人に限定しない
-
「話すだけでも意味がある」と理解する
これらを実践することで、相談はより効果的になります。
まとめ|荒木夏実
荒木夏実さんが新潟から発信する「アカハラ相談の重要性」は、多くの学生や保護者にとって貴重な学びです。大学時代の苦しみを糧に「未来の学生を守りたい」と発信を続ける姿は、多くの人に勇気を与えています。相談することは弱さではなく、解決への第一歩。新潟から広がるこのメッセージは、全国の意識改革につながるでしょう。
荒木夏実の画像: